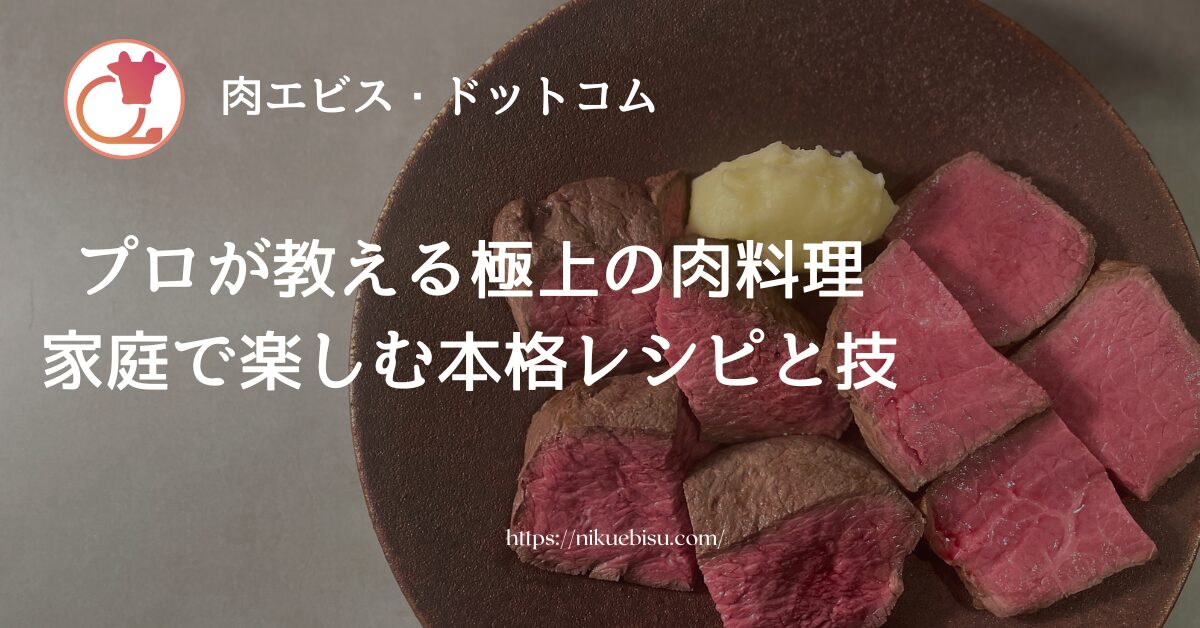独自ブランドを守り続ける赤毛和牛とは?
近年、赤毛和牛が注目され全国で
その人気が高まっています。
あなたはもう食べましたか?
赤毛和牛(あかげわぎゅう)が
他の牛肉と何が違うのか一度食べた方なら
ご存知だと思うのですが
その理由は赤身とサシの絶妙なバランス。
しっとりとジューシーな肉質は
脂っこい霜降り肉に飽きた方には
たまらない旨さを含んだ牛肉だと感じます。
もともとは「熊本」と「高知」の2大産地
今や全国に肥育牧場が
広がりつつある赤毛和牛ですが、
じつは「熊本」と「高知」
この2つの土地から誕生しています。
どちらも和牛の中の褐毛和種という
同じ品種ではあるのですが
高知は県内だけの肥育に留まり、
独自の方法で「土佐あかうし」という
ブランドを守っています。
その一方、熊本の赤毛和牛はというと
北海道や東北の他、四国にも生産地が
各地に広がり赤毛和牛の普及に力を入れています。
ですが未だにその数は減少傾向にあり、
国内で飼育されている
黒毛和牛は1800000頭に対して
赤毛和牛は24500頭程度。
なぜこれほどまでに赤毛和牛の
頭数が減少してしまったのでしょうか?
赤牛が希少な理由
かつて日本では、外国産牛の輸入が
解禁されたことによりアメリカや
オーストラリアから安価なものが次々と
入荷することになった時代がありました。
その時、価格競争を恐れた
畜産家の方達が差別化を計ろうと
霜降りに路線を切り替えたことを
きっかけに国内全土で進められていったのです。
それに伴い、肉の格付け制度が設けられ
脂身の多い霜降りほど市場価値が高いものと
して価値が決められてしまいました。
そうなると赤毛和牛は低い格付けで
安価な取引をされるようになり
生活のままならない牧場は
次々と閉鎖に追い込まれてしまったのです。
霜降り肉にシフトすることなく守り続ける独自ブランド

(阿蘇で見かける赤毛和牛(通称:あかうし)の群れ)
そのふるさとを尋ねて、熊本県阿蘇を訪れました。
熊本空港からはレンタカーで1時間、
熊本城のそびえる市街地とは2時間ほどの
距離が離れている「阿蘇 産山村」
見渡す限り広がる牧場に
放し飼いにされている牛を至る所で目にします。
6〜7頭で群れを作り昼夜ともに
一緒行動しているというあか牛は
天然の牧草を思う存分食べて、のびのび
ストレスなく育ちます。
恵まれた自然の中、ここでの赤毛和牛は
環境に合わせた伝統的な飼育法がされています。
環境に合わせた「夏山冬里方式」

(生まれたばかりの仔牛:
このあと体調に問題がなければ母牛とともに牧場に放されます。)
標高の高い場所にある阿蘇では
気温の高い季節でも涼しく快適に過ごせますが
冬になれば雪も降るほど気温が下がるといいます。
暑さの苦手な牛にとって阿蘇の環境は
とても居心地のいい場所ではありますが
冬の雪山では大好きな牧草も食べられ
なくなるため牛舎に迎え入れます。
「夏は山へ上げて、冬は里へ下ろす」という
伝統の飼育法が今でも実践されているのです。
春に生まれた仔牛たちは牧場を
駆け回り元気にすくすく成長します。
秋の深まる頃には、
見違えるほど体重が増えたくましい姿に
なって母牛とともに里へ下りてきます。
和牛といえば、黒毛和牛のような
サシ(脂)が入った霜降り肉をイメージされる
ことが多いですが、牛舎から出ることなく
濃厚飼料と呼ばれるものを中心に
育てられることが一般的です。
その肉質は柔らかくとろける
食感を生み出しますが運動もせず
牛舎の中で成長する牛たちが
果たして健康的といえるのでしょうか?
私たちがイメージする「良質な和牛」は、
肉本来の味わいが楽しめる
赤身主体の肉質です。
そのぶん、感じる食感は霜降りより
しっかり弾力がありますが、噛むほどに
ジュワーっと旨味が溶け出します。
その唯一無二の美味しさを
生み出している赤毛和牛は
夏山冬里方式を用いた飼育方法で
母牛と仔牛を一緒に愛情を持って
成長を見届けています。
いい草がいい牛を育てる

農家さんは信念のもと栄養たっぷりな
牧草と野山を駆け回ることで健康的で
引き締まった肉質に育て上げています。
本来草食である牛が
大好きな天然の牧草を食べています。
赤牛農家さんは牧草が枯れないよう
環境に注視し毎日広い牧場を見て回り
牛1頭づつの体調を気にかけます。
ここ阿蘇では牛たちが飲む水も特別でした

(底までキレイに透き通って見える水源)
阿蘇を支える清流
今回、訪れた「阿蘇 産山村」では
日本名水百選に選ばれている池山水源から
生活用水のほか農作物や家畜用に
枯れることのない清流を使用しています。
牛舎にも源泉を引き込んで
牛用の飲用水になっています。
この地域では天然の清らかな水を
使用した、米や野菜もすべて
新鮮で美味しいものばかり。
現地の方にきいたお話では
蛇口から出る水はすべて源泉を使用して
いるので冷凍庫で凍らせると一点の曇りのない
クリスタルのような氷ができ上がるそうで
なんとも羨ましい環境だな、と感じました。
池山水源からほど近い場所にある
「山吹水源」にも足を延ばしてみると、
偶然にもこの日は年に1度の清掃日。
神主さんも見守る中、地域の人が総出で水源を
キレイにしている現場に立ち会うことができました。

(お供え物と清めのお酒、水源を見守る地元の神主さん)
熊本県 阿蘇の赤毛和牛は
このような自然環境に恵まれた土地で
生産者さんの愛情を一心に受けて
育てられています。
実際に現地を訪れてみて、
阿蘇の赤毛和牛の美味しさは
「環境による育ちの良さ」だと
深く感じることができました。
この熊本県産あか毛和牛は、恵比寿の赤身肉専門店 QUNIOMI で実際に使われています。