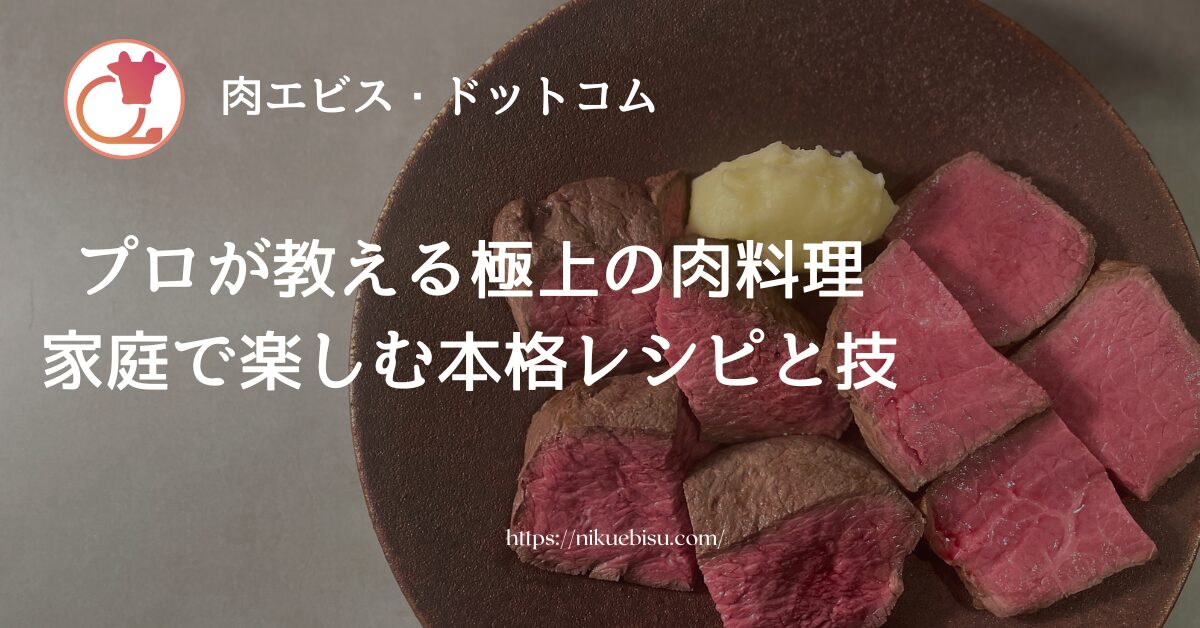和牛赤身肉専門の肉エビスです。
あか牛ファンのあなたにお聞きします。
熊本県や大分県のあか牛ではなく、高知県でもあか牛が飼育されていることを知っていますか?
高知県のあか牛は熊本県のあか牛よりも少ないです。
2018年度 高知県畜産振興課調べによると、年間出荷頭数が約470頭しかいない大変希少な牛です。
そんな希少な土佐あかうしの名前で親しまれている、土佐あか牛を・・・
ついに!視察してきました。
このページでは、高知県のあか牛ブランド“土佐あか牛”について現地レポートも
兼ねて解説をします。
このページをお読みになることで、「絶対に土佐あか牛を食べたい!」と思うでしょう。
楽しみにお読みくださいね。
土佐あか牛と熊本県のあか牛との違い

土佐あか牛と熊本のあか牛は同じあか牛という名前ですが、牛の見た目からことなります。
画像をご覧いただくと分かりますが、同じ褐毛和種(赤毛和牛)とは思えないくらい違います。
上:熊本あか牛:下:土佐あかうし
土佐あかうしの顔は鹿(バンビ)に似ている顔だと感じました。

アイシャドーをしたようなパッチリとした目。
よく目を凝らしてみると…。蹄や尻尾の先、鼻先も黒色です。タテガミも黒です。
熊本、高知どちらのあか牛も見ているので甲乙はつけ難いですが、牛の可愛さでいうと土佐あか牛は可愛いです。
人懐っこく、皆の掌をペロッと舐めていました。
熊本県のあか牛もかわいいですが、鹿というよりも牛らしい立派な牛という印象です。
あか牛の祖先
熊本系のあか牛の祖先は韓国の韓牛と呼ばれる、食用牛とスイスのシンメンタール種を掛け合わせて誕生しました。
前の章で触れましたが、褐毛和種(あか牛)には2種類のあか牛がいます。
“熊本系褐毛和種”と“高知系(土佐)褐毛和種”です。
熊本系のあか牛は熊本県を起点に大分県、長崎県宮城県、北海道・・・など
最近では“あか牛”を育てる方が全国で増えていますが、全て熊本系のあか牛です。
対して、高知系(土佐あか牛)褐毛和種は高知県でしか飼育されていません。

それに、熊本系あか牛は肉質などの改良を重ねて、今の食肉の味わいがあります。
しかし、土佐あか牛は改良をしたくても、そもそも改良をするほどの頭数がいないです。
なので、土佐あか牛の肉質の特徴は、昔ながらの肉らしい味わいがあり柔らかい赤身が特徴的です。
高知県と熊本県のあか牛ともに飼育頭数に問題あり

高知県の土佐あか牛の生産飼育頭数は、前述しましたが極端に少ないです。
熊本系と違い、高知県でしか飼育されていません。
誤解しないでほしいのですが、決して熊本県のあか牛の飼育頭数が多いわけでもありません。
どちらの赤牛も数がいません。
高知県の場合。農家の方が高齢化で、赤牛の飼育のヤリ手がいなくなり、今よりも激減してしまうと…。
冒頭でお伝えした生産量の維持もできなくなります。高知県からすれば死活問題であり、和牛を守る意味でも大問題なのです。
最近、ヘルシー志向が高まり和牛赤身肉にも注目が集まってきています。
和牛赤身肉の認知度も、以前と比べると確実に上がってきています。
土佐あか牛を食べた方は分かりますが、熊本系のあか牛とは違う美味しさが土佐あか牛にはあります。
一言でいうと、肉の味が熊本系よりも濃く感じるとともに、脂っこさは一切ないので食べやすいです。
希少性だけではなく、肉の味わいも今の時代にあっている、などの理由で人気のある和牛になりました。欲しがるお店や食べたい方が急増しています。
これから解説する、こんな理由もあって今では“手に入れたくても入れることができない”幻の和牛肉になっているんです。
和牛肉はアメリカ産のようにホルモン剤を使い早く育てることがないため、子牛が生まれて肉になるまで、最低でも2年半の時間が必要です。
赤身肉ブームになっても、子牛の数が急に増えるわけではないので、幻の和牛はさらに幻となってしまいます。
もし、あなたが土佐あか牛の肉を食べる機会があったら、迷わず予約した方がいいです。今後は、食べれなくなるかもしれないほどの肉だからです。
肉好きならば一度は味わっておいたほうがいいかもしれませんね。
土佐あかうしの産地

高知県全域で飼育をしているようですが、肥育(肉用)として飼育している方と、飼育(子牛)を産ませるために育てている農家があります。
高知県の室戸岬周辺や土佐清水などで、放牧している姿を見ることがありますが、こちらは肥育をしているのではなく飼育用として育てています。
肥育用の土佐あか牛を多く育てているエリアは、この後にご紹介する高知県にある嶺北地区が主な産地です。
嶺北地区は天空の楽園

先日、嶺北地区を訪れたときの画像です。
嶺北地区は四国の真ん中辺りに位置してます。
高知県大豊町、本山町、土佐町、大川村の4つの町村です。

嶺北地区は日本一水がキレイと呼ばれている吉野川の源流地域です。
美味しい水のある場所には美味しいお米とお酒があります。

画像は山間部ならではの棚田です。
この日は天気があまり良くなく曇っていましたが、山の間には霧もやがあり、下には一面。
キレイな緑色した稲が植えられている棚田が広がっています。
この棚田を見にワザワザ都市部から見に来る方がいるそうです。

棚田に植えられているお米は、まだお米になっていないのにすでに行き先が決まっているそうです。
棚田の景観だけではなく、米の味わいも別格なようですね。
一度、この棚田で作られたお米を食べてみたいものです。
嶺北地区は標高200m〜1800mの山岳地帯です。
高い場所は天空のような雲が多いです。
緑が多いので楽園のように見えます。
この地形はとても寒暖の差が激しく、この地で採れる野菜も他のエリアで採れる野菜と比べて、味が濃く、瑞々しいのが特徴です。
これは産地を回っていて感じたことですが。美味しい水がある場所には必ず素晴らしい“和牛”がいます。
嶺北地区はまさに「土佐あか牛の聖域」と表現しても言い過ぎではないと思います。

この後の章で「なぜ聖地なのか?」を説明します。
土佐あかうしの牛舎を見学

今回特別に無理言って土佐あか牛がいる、牛舎を拝見させていただくことができました。
川井さんです。
嶺北地区には、川井さん以外にも多数あか牛を育てている方がいますが、どれも数十頭の規模ばかりです。
ちなみに同じ和牛でも、黒毛和牛を育ててる農家の方は最小規模でも100頭からです。いかに高知県で和牛の土佐あか牛を育ててる方が少ないのが分かると思います。
川井さんはこの辺りで一番大きい300頭ほどのあか牛を育てている一貫農家さんです。
和牛農家の仕組みをよくご存知ではないと思うので説明すると…。
和牛農家といっても3種類あります。
A)飼育農家
子牛が生まれるように和牛を育て、子牛が生まれてからおよそ10ヶ月〜12ヶ月ほど育てます。
それから子牛販売のセリに出して、肥育農家に販売をする農家です。
B)肥育農家
子牛をセリ場で購入してきて、肥育作業(土佐では24〜27ヶ月間 )をする農家です。
肥育する期間はマチマチですが、霜降り肉として高額で取引される黒毛和牛の銘柄牛などは、肥育する期間が厳重に決まっています。
黒毛和牛は決められた肥育期間に満たないと銘柄牛として認められませんし、中には格付け等級A4、A5だけ銘柄牛と認めるような制度もあります。
C)一貫農家
AとB両方を行う農家
全てを行うのである程度の規模が必要です。
ですので、限られた農家だけしか一貫農家はできません。
土佐あか牛と黒毛和牛

川井さんの牛舎を拝見して不思議に思ったことがありました。
黒毛和牛もいます。
というか、一緒の部屋で同居しているんです。
赤と黒が同居しているなんて…
初めてでした。
川井さんのところでは子牛の時から、赤と黒を一緒に育てているようです。
違う和牛同士だと気性の違いなどがありそうですが、お聞きしたところ。
土佐あか牛は、とにかく大人しいから喧嘩もしないそうです。
柵から手を伸ばすと黒毛も餌をくれるのではないかと思い近寄って来ます。
でも、土佐あか牛の方が猛烈に人間に近寄ります。
ラブコールみたいです。
頭を撫でようとしても逃げる牛は少なく、人間の腕を大きな牛タンでベロ〜〜ンと舐めていました。
人懐っこいです。
ちなみに赤毛和牛は土佐あか牛として出荷しますが、黒毛和牛は土佐和牛として出荷するそうです。
土佐あか牛の放牧を見学

川井さんのところでは、牛舎だけしか見ることができなかったので放牧された「あか牛を見たい!」と思いました。
以前から懇意にしている方に「放牧している姿を見たい」と聞いてみると…。
どうやら高知市内で土佐あか牛を放牧している場所があるようです。
市内は駅前はビルが立ち並んでいます。
そんな場所で放牧されているなんて…。
「ぜひ見たい!」
と、お願いして特別に見せていただくことができました。
飛行機と土佐あか牛

案内された場所は高知龍馬空港から車でわずか5分の場所でした。
「高知大学 農林海洋科学部」と書かれた表札を見たときは驚きました。
このような場所で、本当に土佐あか牛を放牧しているのだろうか…。
今回、大学の許可を特別にいただき、大学で土佐あか牛の生体や繁殖研究をしている施設を見せていただくことができました。
先に牛舎を見させてもらうと、かわいらしい顔をした“土佐あか牛”たちが干し草をムシャムシャ食べていました。

中にはまだ耳にタグが付けられてない、昨日生まれたばかりの赤ちゃん牛まで見ることができました。

大学生が毎日、牛の世話をしているので、あか牛は大声でモーーーと泣くことはありませんでした。
愛情を込めて育てているのが伝わってきます。
【超希少】土佐あかうしのオス

放牧の土佐あか牛とやっとご対面がしました。
これを放牧なのか?という声もあると思います。
自らの意思で自由に動き回りながら牧草を食べているので“放牧”と呼んでもいいと思います。
試験的なので小さな群れですが、メスが数頭と子牛が数頭真ん中には他のあか牛と体つきや顔つきが違う牛がいます。

彼はオスなんです。
画像を見ていただくとわかりますが、目の周りが黒くパンダのような顔がオスの特徴です。
なぜ、一頭のオスと多くのメスを一緒に放牧をしているのか疑問に思うでしょう。
自然交配をするためです。
例えば、群れにオス牛2頭とか離してしまうと、生まれた子牛はどちらのオスの遺伝子を持って生まれたのか、分からなくなります。
超わかり易く説明すると、このオス牛は種牛です。
種牛に選ばれる条件は様々ですが体つき肉つき健康面など多面的に見て、優秀だと思われるオスが種牛になります。
牛の世界はオスは人間と違い大変ですね。
本来は土佐のあか牛は大人しい筈ですが、オス牛は別格でした。
群れの近くに寄っていくと…。
一気に警戒モードに入り、コチラの動向を常に見張っていました。
子牛たちは群れの内側に避難させて、オス牛はジワリジワリと近づいてきます。

あと一歩群れのテリトリーに入ると猛突進してきそうな勢いです。
“一触即発”の雰囲気です。
あとで知ったのですが、牛飼いの間でもオス牛には不用意に近づかないそうです。
猛突進されて命を落とす恐れがあるらしいです。※早く言って欲しかった・・苦笑
貴重なオス牛も見ることができました。
ご協力ありがとうございました。
土佐あかうしの肉は評判が良い

土佐あか牛の身質は赤身が主体です。
サシはありますが、他の和牛と比べてしつこい脂ではないのでサーロインステーキで食べても美味しく食べることができます。


(この2枚の画像は現地で食べたステーキです。)
「土佐あか牛」の希少性については、ここまでお読みなれば十分分かったと思います。
それでも。
もし幸運にも土佐あか牛を食べることができるならば、オススメの食べ方はステーキが一番です。
ローストビーフも美味しいですが、肉そのものをガッツリ味わうならば厚みのあるステーキが最高です。
高知県民も中々食べれない幻の肉

高知県はあか牛の産地ですが、地元の人でもあか牛を一度も食べたことがない、という方もいます。
特にステーキとして人気ある部位に限っては、東京や大阪などの都市部に回されます。
都市部の方が高く売れていくことを考えると仕方ないかもしれません。
土佐あかうしが恵比寿で食べれる

当店は都内でも和牛赤身肉を専門に取り扱うお店です。
今回ご案内した土佐あか牛のステーキをご提供している都内でも珍しいお店です。
熊本県のあか牛も扱っているので、仕入れができた順番にメニューに載せるようにしています。
できるだけ、土佐あか牛の良さである「赤身の味わい」を食べた方には堪能していただきたい、と思うので。それを生かすような調理方法で提供をしています。
フレンチの技術であか牛を食べる

「良い料理は素材選びで決まる」と言われるように、出来るだけ「良質な食材の良さ」を引き出すように心がけています。
赤身肉の火入れは難しく熟練の技が必要です。
赤身肉は強火で焼くと、身が縮んだり焼けた部分が苦くなったりするので素材の味わいが台無しになります。
そこで、30年あまりフレンチに携わってきている知恵と経験をもとに、独自の技術で「土佐あか牛」の赤身肉を火入れをしています。
シットリジューシーの赤身肉に仕上げているので肉が固くて食べれないことはありません。
噛むごとに肉汁が出てくるので、いつまでも口の中で噛んでいられます。
土佐あか牛は希少過ぎて入荷が不安定です。もっと定期的に食べる方が増えればいいのにと思います。
外国産の安くホルモン剤を使って大きくして、肉の味がスッカスッカの牛肉と比べると、和牛(黒毛、赤毛、短角)は人体に影響が出やすいとされるホルモン剤を一切使わず、手間暇かけて愛情を注ぎ和牛を育ててます。
日本が誇る和牛文化が残っていけるように、私たちが率先して消費していきましょう。