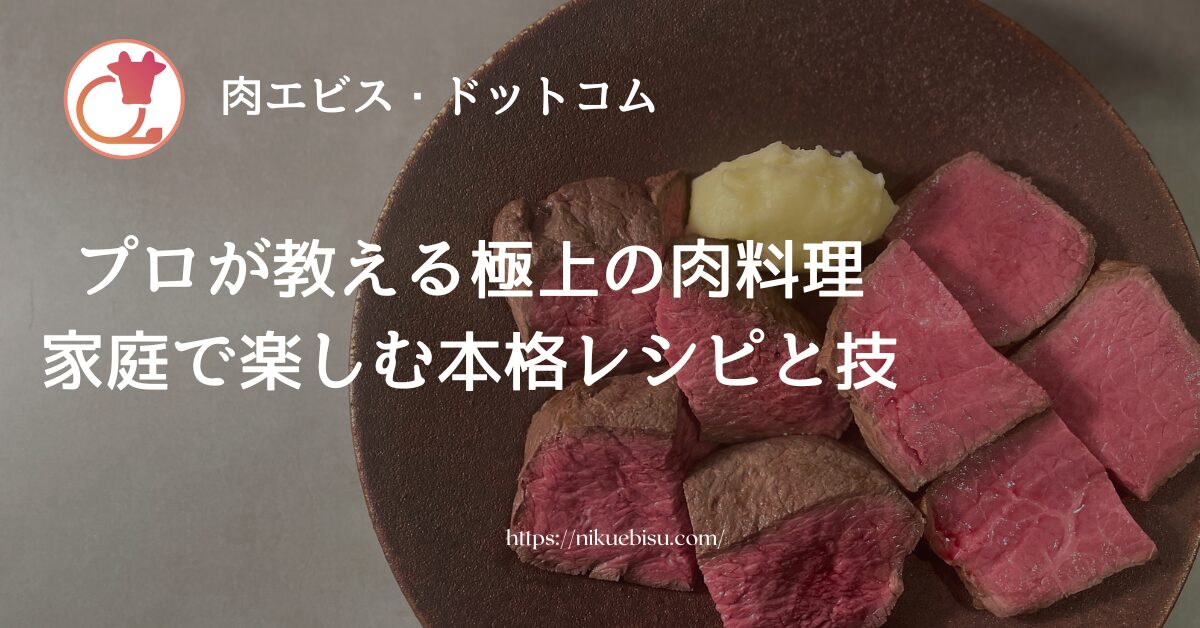こんにちは。
和牛赤身肉専門の肉エビスです。
近頃はインターネットを使えば、食材を全国からお取り寄せできる時代になりました。
現地までわざわざ調達しに行かなくても、画面で選んだものが数日のうちに自宅へ届けられます。
北海道の野菜や三陸地方の魚介、宮崎県の牛肉…
美味しい食材が簡単に手に入るので本当に便利です。
ですが、その一方。絶対に手に入らない食材もあります。
こだわりが強い、わずかな量しかない、信頼した人にしか売らない・・・など。
その理由は様々ですが、インターネット上では公開されません。
公開されたとしても超がつくほど高額で、金持ちの肉好きにしか買えないレベルです。
現地に行かないと繋がることができないため、一般では購入できないようになっています。
当店が扱っている赤牛もその中の一つです。
正式名称は赤毛和牛(あかげわぎゅう)通称:赤牛(あかうし)と呼ばれています。
どのような肉質かといえば、赤身が美味しい肉として霜降りの黒毛和牛とは違った旨味を感じることができます。
とくに、今回ご紹介する熊本県阿蘇にある産山村の農家さんでは、「どうしたらもっと赤身を美味しくできるか」ということを追求しながら飼育されているだけに、
じっくりと焼き上げるステーキは、口の中でしっとりとジューシーで噛むほどに肉汁の旨味が溢れ出ます。
赤身の肉はとにかくデリケートです。
育て方や飼料の配合など産地でかなり違いがあります。
赤牛は熊本県のほか、大分県や高知県、東北仙台、北海道でも飼育されていますが、
当店では赤身肉の美味しさを、ストレートに感じさせてくれる阿蘇の産山村の赤牛が最高ではないかなと思っています。
「なぜ?産山村の赤牛は特別なのか?」
現地でお伺いしてきた情報をまとめてみました。
赤牛の肉質がいい最大の特徴

じつは、あまり知られていませんが、日本にいる和牛は、ほぼ牛舎の中だけで飼育されていることが多く、阿蘇の赤牛のように自由に放牧されながら成長する和牛は、極少数しかいないのが現状です。
なぜかというと、
肉に脂がたっぷりと入っている、霜降りにするためには濃厚な飼料を与えて、なるべく運動させずに育てる必要があります。
いわゆる肥満のような肉質をワザと作り上げているからです。
そこまでする理由としては、肉のセリ場で格付けによって値付けが大きく変わるからです。
A5という最高ランクの称号が与えられるには肉量があり、多くの脂身が入っているほど高い価格で買い取られます。
肉業界が定めているのは格付けの規定には『和牛』というブランド価値を崩さないためでもあるのですが、
その仕組みが続いている限りは、生産者さんにも生活のために黒毛和牛を運動させずに肥満体へと育てるほかありません。
だからといって、阿蘇の赤牛に濃厚な飼料を、まったく与えていないのかというと、そういうわけではありません。
ある程度、濃厚な飼料を与えることで肉質を向上させています。

一見、すべて草ばかり食べさせて、運動を多くさせた方が健康的で美味しい肉になるだろう、と思うかもしれません。
ですが、実際には肉に臭みが出て風味が落ちます。
そして筋肉質になった肉は、固くてどうしようもなく不味くなります。
阿蘇の赤牛は、仔牛が産まれると山の牧草地に母牛と一緒に放牧されますが、冬が来る前には、牛舎へ移動して干し草の他にも濃厚飼料(稲わら、麦、トウモロコシなど)を食べながら過ごしています。
仔牛のうちに母牛の愛情を受けながら自由に動き回り、栄養たっぷりの母乳を飲んで育った
赤牛はストレスなく病気知らずだそうです。
脂肪が付きすぎることなく、風味が豊かでバランスの良い美味しい赤身肉となります。
赤牛の放牧に欠かせないルールは3つ?

現地まで行くと、涼しい牧草地を赤牛たちがのんびり過ごしている光景を目にすることができます。
熊本県の「阿蘇」という場所は、活発な火山活動によって形成された
世界最大級のカルデラがあり、その周辺の外輪地域を含めて壮大で
美しい景観が広がっています。
ですが、見渡す限り広大な敷地に比べて
「あれ?随分と赤牛の頭数が少ないな」
と感じるかもしれません。
じつは、赤牛1頭に対する必要な面積が決まっているからです。
赤牛が大満足な牧草の広さ
牛たちは放牧されながら、自由に好きな牧草をムシャムシャと食べていますが、その必要とされている広さは
最低1ha(ヘクタール)もあります。
分かりやすく、いったいどのくらいかというと、
1haは「100m×100m」の広さと同等です。
学校にあるプールが25mなので1haというと、25mプールが16個分ある計算になります。
1頭にしては随分な広さが必要ですよね。
そう考えると、栄養満点な牧草を維持して行くのは大変なことです。
さらに阿蘇の牧草地ではまだ条件があります。
赤牛の自由は男子禁制!?

赤牛を放牧する際の条件として、組合で決められた敷地の広さのほかにも、放牧が許されている赤牛はメスだけになります。
メスだけが仔牛とともに放牧される理由としては交配があります。牧草地には赤牛のほかに黒毛も一緒に放牧されているからです。
自由に動き回れる場所で、万が一オス牛を放すと黒毛和牛との混血が生まれたり、血の気の多いオス牛による事故や怪我が増えてしまいます。
少ない家族経営の牧場では、広い敷地内を管理することは到底できません。
そのような理由もありメスだけを放牧させています。
赤牛はグループで夜を明かします
放牧されている赤牛たちは日が暮れると、てっきり牛舎へ戻されるものと思っていました。
ですが、そのまま自由にしておくそうです。
寒さが厳しくなる冬を除いて、春から秋までは牛舎に戻ることなく広い敷地内で暮らしています。
森に狼が住んでいるようなヨーロッパで飼われている羊たちとは違い、阿蘇には赤牛の天敵になる動物はいないので安心ということです。
放牧されている赤牛たちは7〜9頭ほどのグループで行動しています。その中から自然とリーダーになる赤牛が決まるといいます。
その責任感のあるリーダーが、みんなを引き連れて昼間は美味しい牧草がある場所へ誘導したり、夜は安全な木の陰を探して休ませてくれています。
とはいえ、約6ヵ月のあいだ、赤牛たちをほったらかしできません。
農家さんは、赤牛が道路に飛び出さないよう、柵が壊れていないか
チェックしたり、たまに山の斜面から転げ落ちたりする牛もいるそうで、
毎日様子を見に、軽トラックで広い牧草地を探して走っています。
赤牛のために欠かせない危険な作業

阿蘇を一度は訪れたことがある方なら、この景観のすばらしさが心に刻まれて忘れられないかもしれません。
この一面、緑の牧草地にするためには人間が手入れする必要があります。何もしないままでは、木が育ち、森や薮のようになってしまうからです。
そこで、『野焼き』という方法が行われています。
組合の人たちで協力して牧草地を順番に焼き払っているのです。

この野焼きの作業は2月〜3月、春が来る前に行われます。
牧草地をすべて真っ黒になるまで焼き払ってしまうのですが、
その主な理由は3つあります。
・ダニや人畜に有害な虫の駆除のため
・木が成長しないようにするため
・焼けた草木が肥料となって美味しい草を育てるため
野焼きは画像の通り危ない作業です。必要な場所だけ萌えるように最新の注意を払って作業を行なっています。
もし、野焼きを止めてしまうと。赤牛が食べる良質な草花が育たず放牧することができなくなるそうです。
ここ阿蘇では、1000年も前から毎年『野焼き』を繰り返し行なってきた歴史があり、欠かせない作業のひとつになっています。
令和2年1月には、熊本県と阿蘇地域7市町村が結託して阿蘇の
景観を守るために世界文化遺産の登録を目指すという活動を宣言されています。
阿蘇赤牛の誕生秘話

赤牛はいつから阿蘇で誕生して育てられるようになり、ブランド化していった牛なのでしょうか?
もともとは赤牛は役牛でした。
運搬や農耕用として重い荷物を運んだり、畑の土を掘り起こしたりする牛のことです。
現地では「肥後の牛」と呼ばれていたようです。
今よりも小柄だったと言われる肥後の牛は、江戸や明治時代に人々のために活躍していました。
ですが、阿蘇山の噴火で火山灰土の多い地域では、効率よく耕すためには肥後牛を大きくする必要がありました。
そこで、海外から連れてきた大型のシンメンタール種を肥後牛と交配してカラダを大きくした赤牛が誕生しています。
交配の過程では様々な牛が産まれましたが、体格のいい赤毛の赤牛が残されたそうです。
ですが、役牛として大切に飼われていた赤牛も、戦後に開発された農耕用の機械が登場すると、一気に活躍の場が少なくなります。
それと同時期に、『肉を食べる文化』が国内で広まっていたため、赤牛も肉用種として方向転換されました。
阿蘇に暮らす人々にとっては、時代が変わっても牛はなくてはならない
存在として共存共栄のあいだ柄にあると言えるではないでしょうか。
牛たちを放牧させるために野焼きをして管理している牧草地ですが、
それが美しい景観を作り出し阿蘇ならではの風景と、良質な赤牛を作り出しています。
〜続編へ続く〜
和牛赤身肉専門の肉エビスです。 赤牛のことは前編もあるので、まだお読み出ない方はこちらも 合わせてご覧になって下さい。 熊本県の阿蘇は世界最大級のカルデラがある広大な景観が特徴的です。 阿蘇の …
この熊本県産あか毛和牛は、恵比寿の赤身肉専門店 QUNIOMI で実際に使われています。